今回は「オーバヘッドプレスと腰痛の関係」について書いていきます。
オーバヘッドプレスは「フォームのミス」があると腰痛が起こりやすい種目ですが、ミスの出る例では「重量に体幹部が負けている」ことがあります。
特に、オーバヘッドプレスに少し慣れてきて「扱える重量が重くなってきた時期」に多いと感じています。
※実際に筆者や、You Tubeのモデル役のハマダスくんも、腰痛こそないものの、体幹部の負けに試行錯誤しています。
「体幹部が負ける例」は、大きく分けると「2つの場面」で見られ、明らかに動作の違いが見られます。
それに気付かずに重量を増やしても、待っている先は「腰痛」になるのは目に見えています。
なので今回は、
・体幹部の負けが起こりやすい場面と、フォームミスの例
・改善するために取り組んでいるトレーニング
この2つを紹介していきます。
※オーバヘッドプレスの基本フォームはこちらで紹介しています。
- 重量に体幹部が負けやすい2つの場面
- 挙上初期の腰痛の改善方法「股関節伸展」
- 挙上初期〜トップで起こる腰痛改善「腹筋強化」
- オーバヘッドプレスでケガをしない条件「肩周りの柔軟性」
- オーバヘッドプレスの腰痛と体幹の関係 まとめ
重量に体幹部が負けやすい2つの場面
正直、どの場面でも体幹部の負けは見られるのですが、
特にフォームの中で自然に見られやすい「2つの場面」は
・挙上初期〜
・トップポジションの手前
でよく見られます。
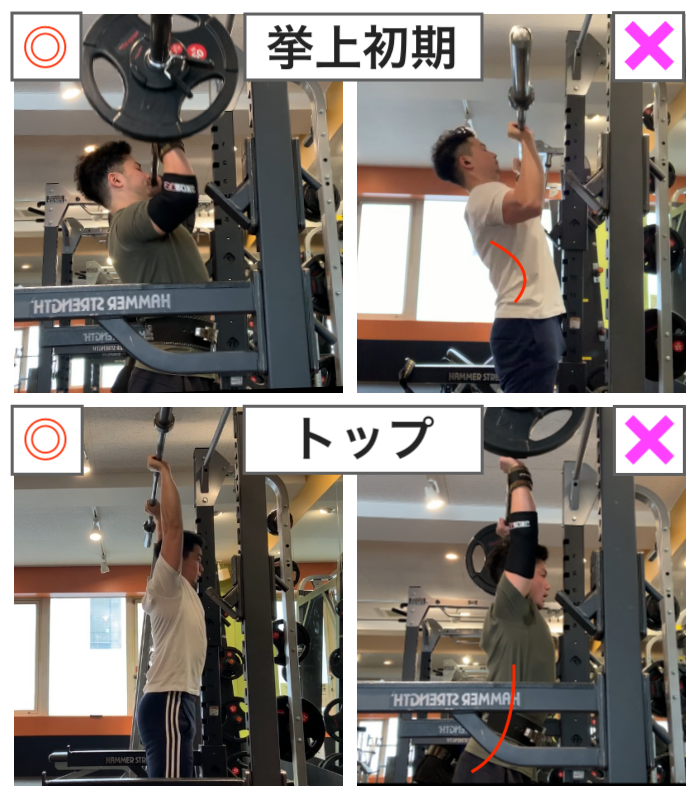
少しセーフティーバーで見にくいですが、×の方では赤線の
挙上初期:腰椎の伸展
トップ:骨盤の前傾+腰椎の伸展
などの「体幹部が負ける」ことを「腰椎伸展(腰を反る)で代償」しています。
代償動作を繰り返すことで、
・筋緊張による腰痛
・腰椎の椎間関節や、靭帯部の痛み
など、「慢性腰痛」にもなりやすい例となります。
これらを解消するためには、
・フォームの熟練度を上げる
・腹筋群の強化を行う
・肩周りの柔軟性をあげる
この3つがポイントになります。
では、それぞれについて詳しく見ていきます。
挙上初期の腰痛の改善方法「股関節伸展」
「挙上初期の腰痛」で多い例が、
「股関節伸展の動きが無く、その代償を腰椎伸展で行っている」パターンです。
「股関節伸展」は、フォーム解説動画でも言ったとおり、
「バーの挙上をまっすぐ行い、下肢の力を伝えるのに必要な動作」です。
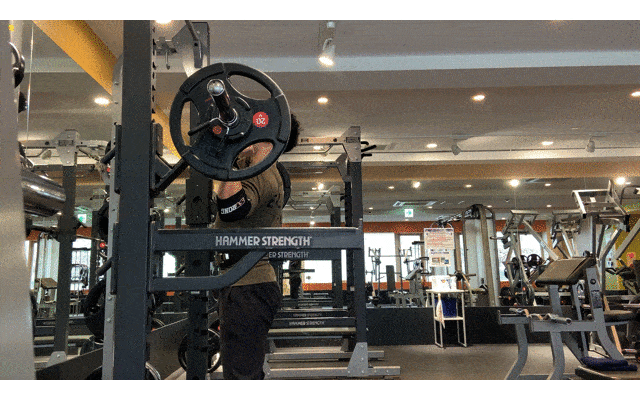
「挙上動作を始める前に、お尻を前に突き出すような動き」が股関節伸展で、この「前に動く移動」が無いと、「腰椎の伸展」で代償してしまいます。
そして、2つの違いが決定的に出るのが「バーと顔の距離」です。
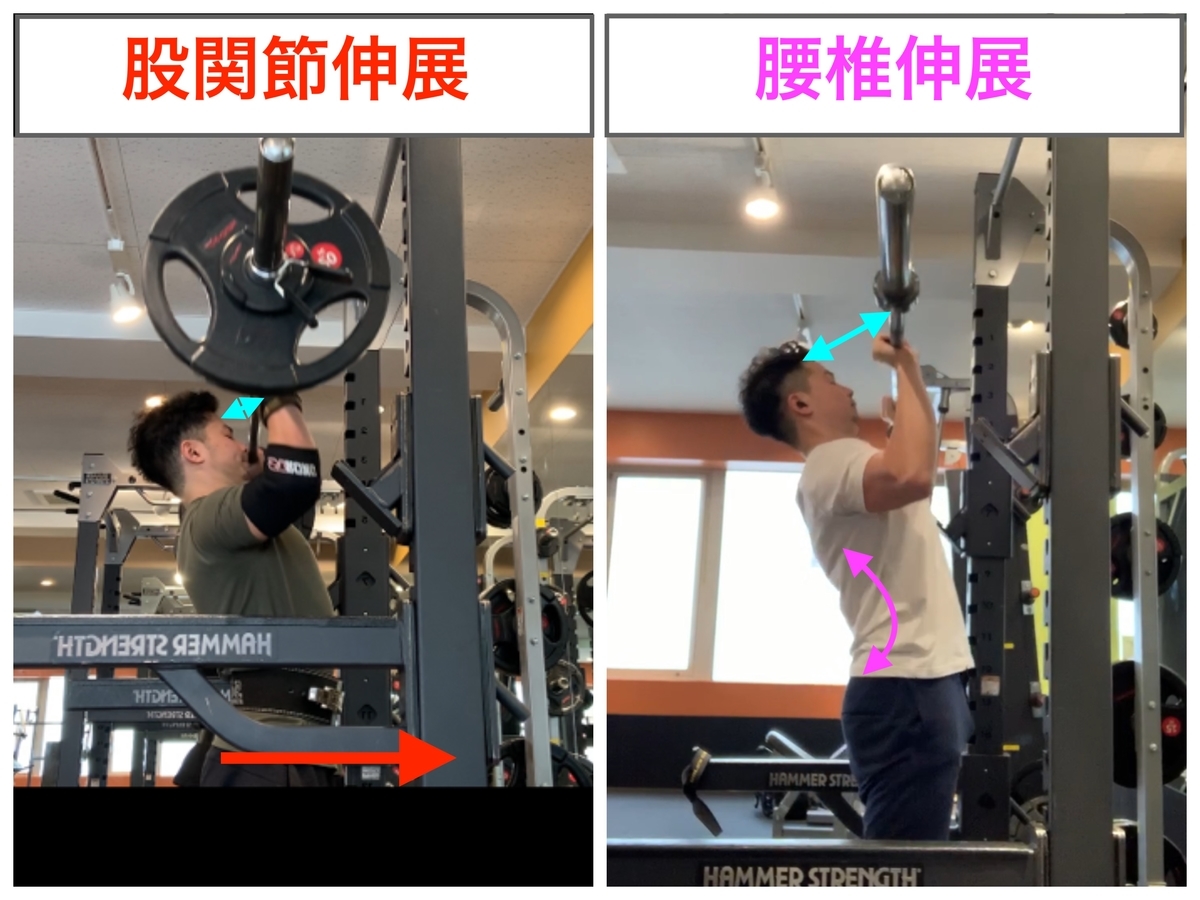
画像の水色矢印が「バーと顔の距離」ですが、
「股関節伸展」では、ほぼスレスレを通過するのに対して、「腰椎伸展」では、バーと顔の距離が遠くなります。
「腰椎伸展」が強く出ると、挙上していく際の重量を「腰で受ける」形になるので、挙上初期に痛みがある方は要注意です。
対策としては、
・フォーム(股関節伸展)の練習を行う。
・腹圧をしっかり高める意識を持つ
が基本になります。
「股関節伸展の練習方法」は、
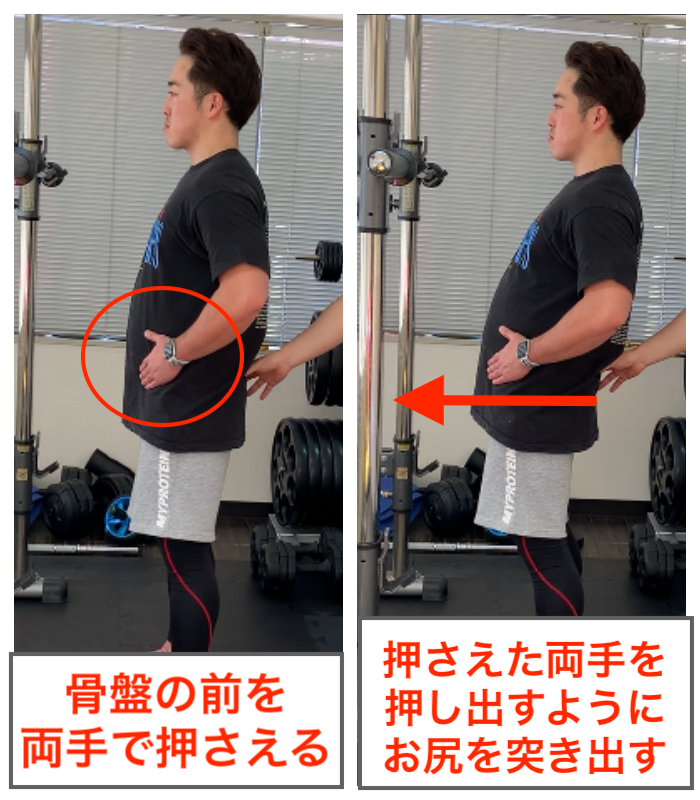
腹圧については「コチラの動画」で紹介しています。
挙上初期〜トップで起こる腰痛改善「腹筋強化」
オーバヘッドプレスの動作の全体を通して、腰痛が起こりやすい原因として「腹筋群の弱さ」があげられます。
先程の「挙上初期」は、フォームの問題も大きかったのですが「トップポジション」に向かうに連れ「腹筋の弱さ」がわかりやすく見られます。
では、初めの画像をもう一度見てみます。
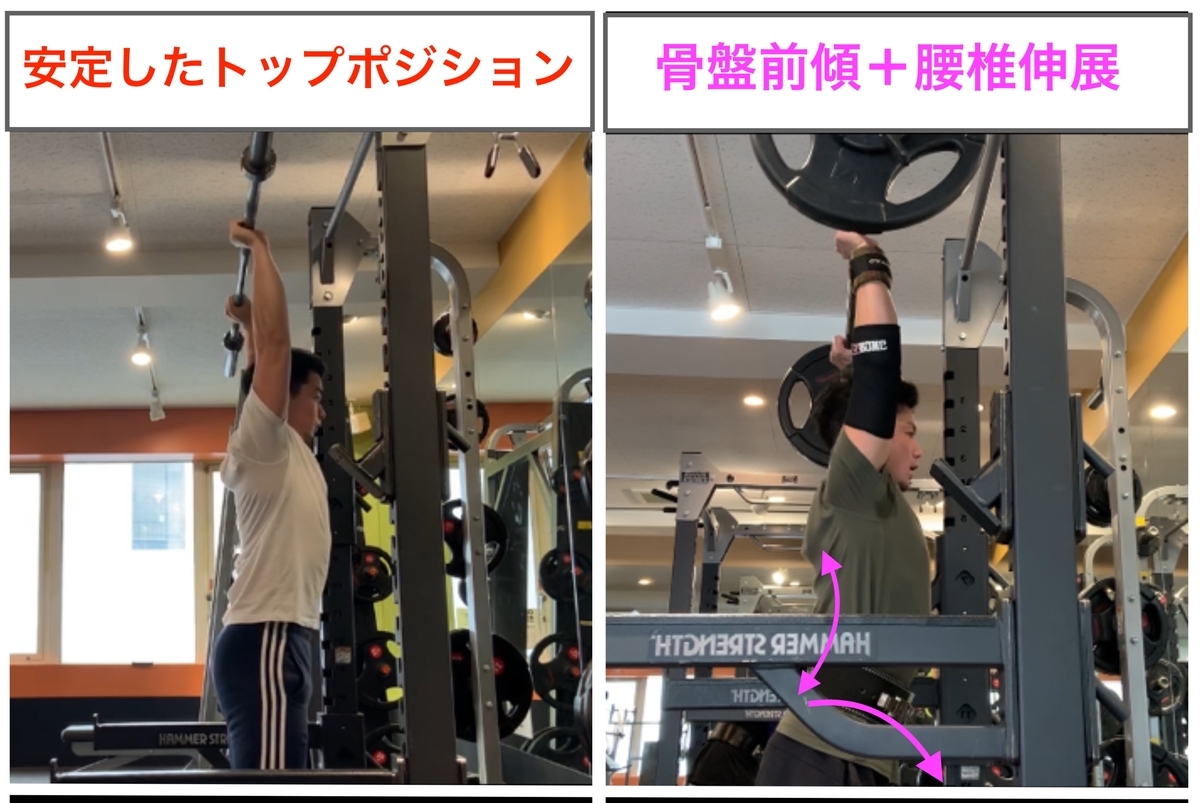
ここで考えられることが 、
・骨盤前傾=「殿部、腹筋群が弱い」ため、負けている
・腰椎伸展=「脊柱起立筋が過緊張」して無理やり支え、腰椎が伸展する
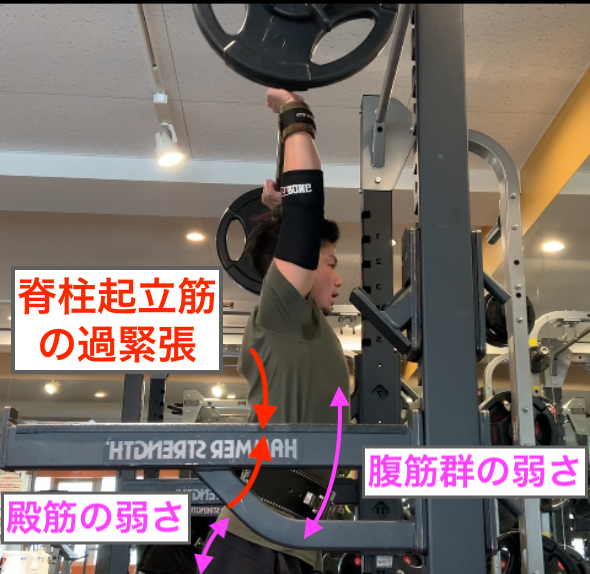
このパターンになる方は、
ナローデッドリフトでも「腰に負担が掛かりやすいタイプ」 だと思います。
ここの課題は明確で
・腹筋群、殿筋の強化
・脊柱起立筋の緊張を取るケア
が重要です。
「腹筋群の強化」
「アブローラー」を使ったコロコロは、とても有効だと思います。
動作はテンポよく行わずに、ゆっくりと丁寧に、無理のない範囲の回数で良いです。
「自分の脊柱のコントロールを腹筋群でしっかり行う」ことが重要で、アブローラで腰が痛くなる方は「腹筋群が働かずに腰椎伸展の運動」を行っている可能性があるので注意してください。
動作はテンポよく行わずに、ゆっくりと丁寧に、無理のない範囲の回数で良いです。
「殿筋の強化」
重心のコントロールと、体幹の安定性の意味でも「ブルガリアンスクワット」なども良いです。
片足種目は、筋の左右差なども出やすいのでメニューに取り入れることで、スクワットなど他の種目にも還元されるのでオススメです。
「脊柱起立筋のケア」
脊柱起立筋は、多くのトレーニングで使われ、特にBIG3を好む方は疲労が溜まりやすい筋肉になります。
フォームローラーや、ストレッチなどのケアは大前提で、「腰椎伸展による多裂筋の緊張」を取ることが「腰痛改善」にとても重要です。
少し動画での紹介が多くなりますが、お時間のある方は是非見てもらうことをオススメします。
では最後に「肩周りの柔軟性」について見ていきましょう。
オーバヘッドプレスでケガをしない条件「肩周りの柔軟性」
オーバヘッドプレスは、スクワットや、ベンチプレスとは違い「頭上にあげる」トレーニング動作になります。
つまり「肩周りの柔軟性」がなければ、腰、肩の怪我の元になります。
※肩、肩甲骨、胸郭の動きを腰椎が代償する。
そこで、肩周りはもちろん「上半身」全ての柔軟性をつけるために、筆者は「ダンベルプルオーバー」をオススメします。
ウォーミングアップとして取り入れることで、「肩周り、肩甲骨、胸郭」の動きが良くなり怪我の危険性を下げることができます。
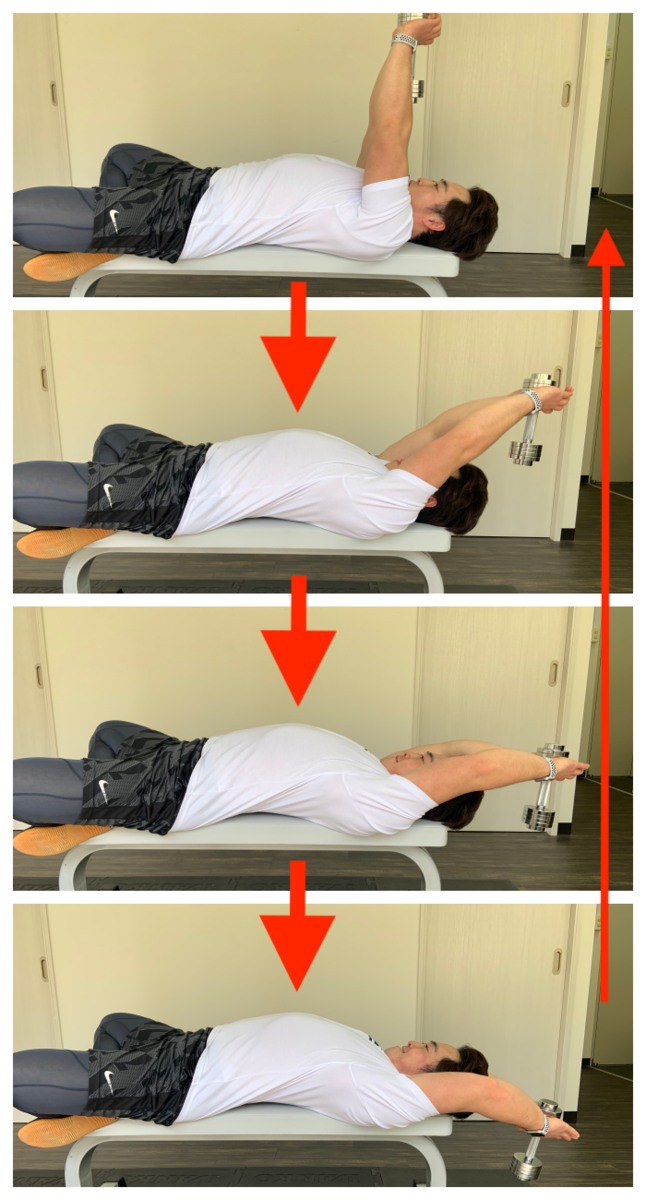
重さは軽めで良いので、「大きな可動域」を意識して「10回2セット」ほど行います。
胸を張り、肩甲骨を下げながら動作を行うことで、「肩、肩甲骨、胸郭」に動きが付き、オーバーヘッドプレスに必要な可動域を得ることができます。
オーバヘッドプレスの腰痛と体幹の関係 まとめ
以上が「オーバヘッドプレスと腰痛の改善方法」になります。
腰痛の原因としては「フォーム」「基礎筋力」「柔軟性」といった様々な要因があり、 オーバヘッドプレスの動作自体が難しく、フォーム習得に時間がかかりますが、「体幹部を含め、全身を鍛えることが出来る」素晴らしい種目です。
そして、オーバーヘッドプレスに必要な「可動域、柔軟性、体幹部の強さ」などは、他のトレーニングにも還元され、特に「BIG3において大きな恩恵」があると感じています。
ジムではあまり見かけない人気の少ない種目ですが、是非取り入れてみてください。
それでは今日はここまで!次回、おたのしみに!
この記事を読んだあなたへオススメ